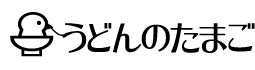冬の海にさざ波が寄せている。
人気の無い砂浜に、錆びついたイーゼルがひとつ立っていた。
「冬の訪れを観測しているのです」
と伸ばした腕の先、鉛筆を定規代わりにして、古ぼけたお絵かきアンドロイドは言った。
古ぼけて曇りと傷が目立つメタリックなボディ。
どこから流れ着いたか分からない彼は、気がつけばこの海岸で毎日のように筆を走らせていた。
「いつもの事ながら上手いもんだね」私は言った。「色使いがすごく綺麗だ」
「今日も見に来たのですね……ええと、メモリーエラーで名前が思い出せませんが、いつもの方」
海辺ノイズ混じりの合成音声が響く。
「上手いのはそのように作られたからです。写真のように景色を写し取り、出力する。私がしているのはそれだけです」
「ううん、それだけじゃないよ。君の絵には君の生きてきた人生が刻まれているように思える。私は君の絵、好きだな」
「機械に人生とはご冗談を。しかし喜んでもらえるのは、良いことです」
彼の目の部分に埋め込まれたLEDがチカチカと点滅した。笑い声のように、ぶおんと言う機械音が鳴る。
私は彼の所作に、『笑顔』を見いだした。アンドロイドである彼に感情は無いはずだけれども。
「絵を褒めていただき、ありがとうございます。ええと……」
「詩緒だよ」
海沿いの三角屋根を指さしながら、私は何度目になるか分からない自己紹介をする。
「そこの家に住んでる女子高生。金原詩緒」
「詩緒。ありがとう、詩緒。私はウテルモーレン。私はあなたの名前を決して忘れないでしょう……ええと」
「詩緒」
「そうだ。詩緒、詩緒――」
彼は私の名前を復唱する。
が、明日の朝にはもう、私の名前は忘れ去られているだろう。
だって彼のメモリーは壊れつつあるのだから。
***
記憶領域にエラーが発生したアンドロイドの寿命は――残念ながら長くない。
いずれ動作プログラムのある領域が駄目になり、ただのガラクタと化すのだ。
***
「なんだよ。壊れるのがそんなに嫌なら、修理すればいいじゃないか」
彼について初めて相談したとき、学校の悪友はそう言った。
「新しいパーツを買ってさ。メモリーも取り替えて。それじゃ駄目なのかよ」
「駄目なんだよ、斉藤」
私は首を横に振って答える。
「旧式すぎてパーツが無いんだって。それに、取り替えても意味がないんだよ。パーツを取り替えたら、彼の個性は消え去ってしまう……」
「個性?」斉藤は首を傾げた。
「機械だろ、そいつ。同じ絵を描くように作られてるのに個性?」
詩緒……お前言ってることが変だぞ? そんなものあるわけないだろ?」
斉藤の言うのも尤もだ。量産型の絵画機械である彼らは、皆同じ絵を描くように作られている。
でも、彼には確かな個性があった。
年月の積み重ねによって変色したレンズ。わずかに狂った色彩センサー。錆びついたジョイント。傷だらけのフレーム。欠けたメモリー。
それらが生み出す描線を、色彩を私は愛していた。
まるで人を愛するかのように。
***
「ところで、詩緒。あなたは私に何の用がありましたか?」
「実は、贈り物があるんだ」
私は鞄から毛糸で編んだ手作りのマフラーを取り出した。
彼が首を傾げる。
「私は寒さは感じませんよ?」
「友愛のしるしだよ。いいから、受け取ってよ」
「……それではいただきましょう」
軽く頭を下げた彼の首に、マフラーを結んでやる。
風に揺れる毛糸の帯は、彼の描く夕日と同じ色をしていた。
「ありがとうございます。この事はけして忘れないでしょう……ええと」
「詩緒だよ」
何度教えても、彼は私の名前を忘れてしまう。
けれども、明日の彼には――少なくとも私のマフラーは残るのだ。
***
日が沈み、夜が更けていく。
真っ暗な海から、波の音だけが聞こえてくる。
自室の壁に掛かる、彼からもらい受けた何枚もの絵。
それらをぼんやりと眺めながら、私は彼の事を想う。
私はきっと、いつか彼の墓標を立てることになるのだろう。
砂浜に倒れ伏した金属の体を引きずって、あの寂しい砂浜のどこかへと埋葬するだろう。
私はそこを通るたびに彼の死を悼み、たまに花を供え、そして彼というひとつの存在が永遠に失われたという事に涙を流すだろう――。
アンドロイドの墓を建てるのは、おかしいだろうか?
量産型の機械に、個を見いだすのは変なのだろうか?
けれども私は、それをせずにはいられないだろう。
私にとってあの海辺のウテルモーレンはたった一人しかいない、かけがえのない存在なのだから。
***
私は目を閉じ、ゆるやかに押し寄せる波の音と睡魔に身を任せる。まぶたの裏にいつか来る彼の死が映る。
朝焼けの海。満潮。足下に倒れ伏す古ぼけた金属の体。
イーゼルの錆の匂い。そして寄せるさざ波の中で濡れる、夕日色のマフラー――。